Note:
小松和彦監修の「怪異・妖怪学コレクション」の一冊。大衆文化として消費される怪異・妖怪をテーマとしてアンソロジー。このシリーズ買って読むまでアンソロジーとは知らんかった。
中身はまぁ2000年代における怪異・妖怪論の傑作選みたいな感じだから、当然どれも読み応え十分の内容。特に京極夏彦の「通俗的『妖怪』概念の成立に関する一考察」は小説家だけあって近代以降の「妖怪」という概念について巧く読みやすくまとめてあって良かった。
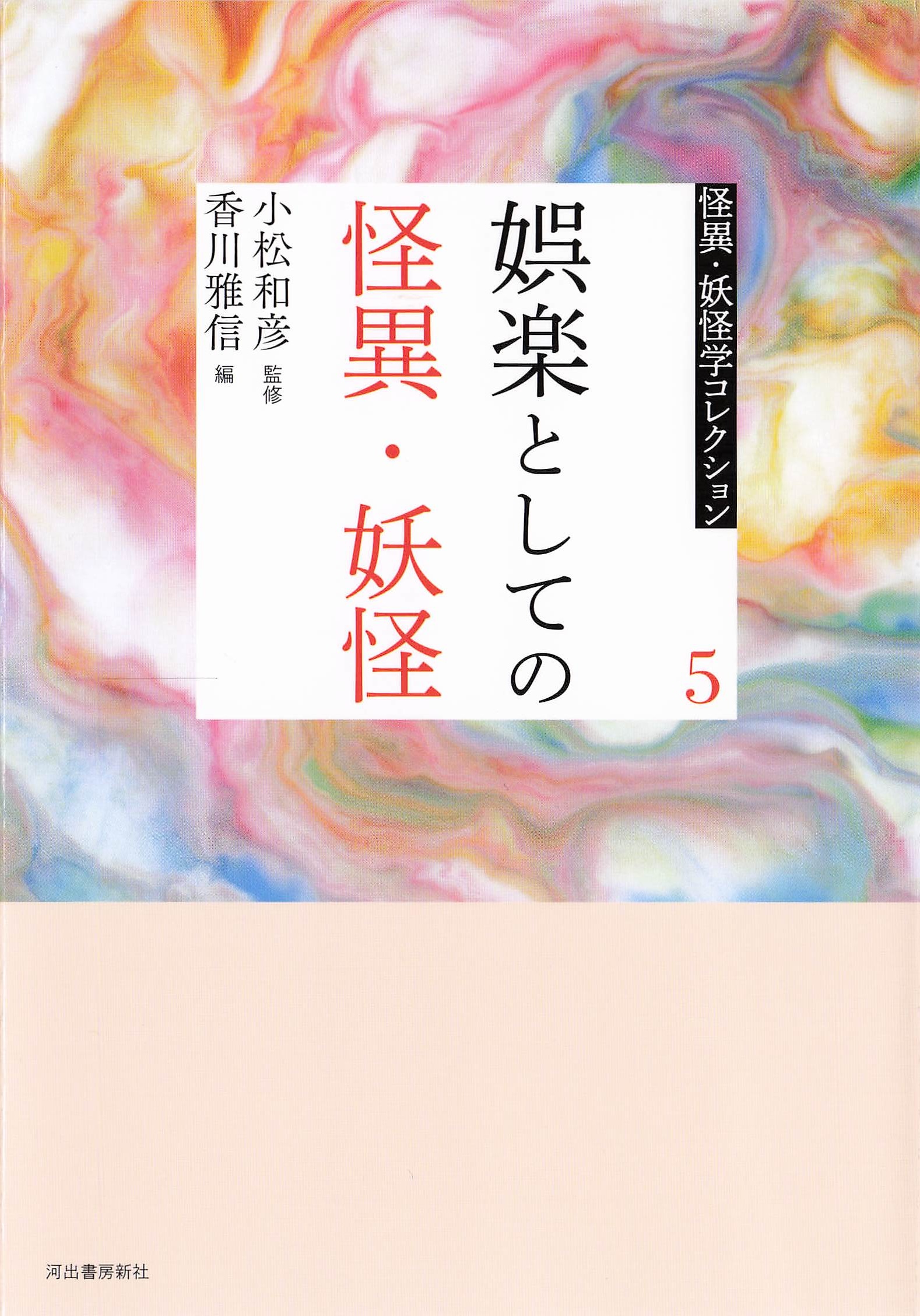
| タイトル: | 娯楽としての怪異・妖怪 |
|---|---|
| 出版種別: | 書籍 |
| 監修: | 小松和彦 |
| 編者: | 香川雅信 |
| 著者: | 橋爪紳也 / 横山泰子 / アダム・カバット / 岩城紀子 / 鈴木堅弘 / 近藤瑞木 / 京極夏彦 / 志村三代子 / 清水潤 / 飯倉義之 / 伊藤慎吾 |
| 出版社: | 河出書房新社 |
| 発行日: | 2025-08-20 |
| 購入日: | 2025-08-27 |
| 読了日: | 2025-09-14 |
| 管理番号: |
小松和彦監修の「怪異・妖怪学コレクション」の一冊。大衆文化として消費される怪異・妖怪をテーマとしてアンソロジー。このシリーズ買って読むまでアンソロジーとは知らんかった。
中身はまぁ2000年代における怪異・妖怪論の傑作選みたいな感じだから、当然どれも読み応え十分の内容。特に京極夏彦の「通俗的『妖怪』概念の成立に関する一考察」は小説家だけあって近代以降の「妖怪」という概念について巧く読みやすくまとめてあって良かった。
総論 娯楽としての怪異・妖怪(香川雅信)
【Ⅰ 娯楽と妖怪】
化物屋敷の誕生(橋爪紳也)
遊びの中の妖怪たち――近世後期における妖怪観の転換(香川雅信)
【Ⅱ 江戸の化物文化】
素人の演出する怪談芸――江戸時代の「妖怪手品」について(横山泰子)
豆腐小僧の系譜――黄表紙を中心に(アダム・カバット)
化物と遊ぶ――「なんけんけれども化物双六」(岩城紀子)
春画・妖怪画・江戸の考証学――〈怪なるもの〉の視覚化をめぐって(鈴木堅弘)
「妖怪」をいかに描くか――鳥山石燕の方法(近藤瑞木)
【Ⅲ 現代大衆文化と妖怪】
通俗的「妖怪」概念の成立に関する一考察(京極夏彦)
「見世物」から「映画」へ――新東宝の怪猫映画(志村三代子)
一九七〇年代の「妖怪革命」――水木しげる『妖怪なんでも入門』(清水潤)
鎌鼬存疑――「カマイタチ現象」真空説の受容と展開(飯倉義之)
ライトノベル異世界転生物における異世界の生成――モンスターの和洋混淆状態を手がかりに(伊藤慎吾)
解題(香川雅信)